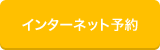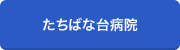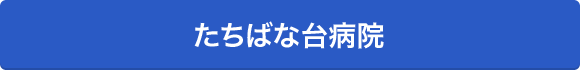子どもの睡眠 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進

今回は、日本の子どもたちの睡眠状況について解説します。
日本の子どもたちは世界でも寝ない子どもとして知られています。
さて、睡眠不足はどのような影響を子どもたちに起こすのでしょうか?
■日本の子どもたちは基本的に「睡眠不足」
そもそも子供はどれくらい睡眠時間が必要なのでしょうか。
厚生労働省によると、成人は6時間以上を確保することを睡眠しているのに対して、
- 1~2歳児は11-14時間
- 3~5歳児は10~13時間
- 小学生は9~12時間
- 中学・高校生は8~10時間 の睡眠時間を確保することが推奨されています。
それに対して、日本の子どもたちの睡眠の状況は芳しくありません。東京大学では腕時計型のウェアラブル端末を使って子どもたちの睡眠の実態を調べる大規模なプロジェクトを進めており、7700人分のデータを集めて中間報告を行っています。
それによると各年代の睡眠時間は
- 小学1~3年生:8.4~8.6時間
- 小学4~6年生:7.9~2時間
- 中学生:7.1~7.5時間
- 高校生:6.5~6.6時間 となっており、小学生・中学生が1時間近く、高校生は2時間近くも睡眠不足であるとされています。
みなさんが1〜2時間も睡眠時間が短かった日を思い出してみてください。頭もぼーっとして集中できず、仕事していても強烈な睡魔に襲われることはありませんでしたか?
今の日本の子どもたちはそのような状況にあるのです。
(参照:厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針の改訂について(案)」)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001151834.pdf
(参照:NHK「子どもの睡眠 小中高全学年で不足の傾向 大規模調査中間報告」)
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20240318/2000082852.html
(参照:知っておきたい子どもの睡眠)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/josm/3/2/3_127/_pdf/-char/ja
■子どもたちの慢性的な睡眠不足は教育面にも健康面にも悪影響
もちろん慢性的な睡眠不足を野放しにするのは、健康面でも非常に危険です。それは子どもたちも例外ではありません。例えば、一般的には睡眠不足により以下のような影響が出てくるといわれています
【学習面の悪影響】
- 学習した内容が記憶として定着しなくなる:睡眠中は、学習した情報が整理・固定化されるプロセスが進むため、十分な睡眠がないと記憶力や学習効率が低下します。
- 集中力と注意力が低下する:睡眠不足は、授業中の集中力や注意力の持続を妨げ、学習効果を減退させる原因となります。
- 情緒が不安定になる:十分な休息が得られないと、感情のコントロールが難しくなり、教室内での行動や対人関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
【健康面の悪影響】
- 成長ホルモンの分泌不足:実は、子どもの成長ホルモンの多くは睡眠中に分泌されることがいわれています。そのため、睡眠不足により、十分な成長ホルモンが出ないと成長の妨げになる恐れがあります。
- 免疫機能が低下する:睡眠不足は免疫力を低下させ、感染症などに対する抵抗力が弱まります。
- 代謝機能が落ちる:睡眠不足は、肥満や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めることが示されています。
実際、2022年に日本で41,890人に対して行われた研究によると、夜間睡眠時間が 9 時間以下の子どもは、睡眠時間が十分とれている子どもと比べて
- そわそわしながら話を聞けなくなりやすい(1.26倍)
- 我慢強くいられなくなりやすい(1.27倍)
ということがわかっています。また、夜間の睡眠時間が不規則な子どもも、日中の行動障害も起きやすいこともわかりました。
このように、子どもたちの睡眠は健康面でも教育面でも何よりも大切にしないといけません。
(参照:Association of nighttime sleep with behaviors in Japanese early childhood:日本の幼児期における睡眠と行動との関連)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ped.15354
■どうして子どもたちは「睡眠不足」なのか
では、なぜ子どもたちは睡眠不足に陥っているのでしょう。
厚生労働省が発行している「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」では、子どもたちが夜更かしする原因として以下のことを挙げています。
- 部活動や勉強で夜遅くまで活動することが多くなるから
- 友人のつきあいが夜遅くになることがあるから
- デジタル機器を夜遅くまで使用することがあるから
- 成長とともに、本来の睡眠・覚醒リズムが後退しやすいから。
- 学校のない休日に睡眠負債を解消するために起床時刻を遅らせることにより、午前中の時間帯に日光を浴びることができず、睡眠・覚醒リズムは後退しやすくなるから。
他にも朝食を食べなかったり、起床時に太陽の光を浴びなかったり、運動せず座りっぱなしの時間が長くなると睡眠不足に陥りやすいこともわかっています。
特に影響が大きいのはスマホやインターネットです。
2021年に日本で発表された中高生約24万8千人(2012・2014・2017年の全国調査データ)を分析結果では、平日のインターネット利用が5時間を超えるような子どもでは、睡眠不足(短い睡眠時間)、深夜の就寝、睡眠の質の低下や不眠症状といったあらゆる睡眠問題のリスクが有意に高まることわかっています。とくにSNS利用やオンラインゲームなどは就寝時刻の遅れと強く関連していました。
現代はSNSやデジタル機器の発達、受験の過熱化などにより、夜遅くまで起きるのが「あたり前」のようになってきています。SNSを通じていつでも友人とコミュニケーションをとれますし、スマホでゲームもできます。
確かに色々技術の進歩によりやれることが増えた分、日中に活動しやすくなりましたが、その分だけ最も大切な「睡眠時間」が追いやられてしまっているのです。
(参照:The association between Internet usage and sleep problems among Japanese adolescents: three repeated cross-sectional studies:日本人青少年のインターネット利用と睡眠障害との関連)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34252182/
(参照:健康づくりのための睡眠ガイド 2023)
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
■子どもたちの睡眠不足に大人ができること
子どもは昼間に起きて夜に寝ると言うことがまだわかっていません。それどころか、このような睡眠状況では大人もわかっていないのです。
睡眠負債とは、William C. Dement 教授(スタンフォード大学)により提唱された言葉です。日々の睡眠不足が借金のように積み重なり、心身に悪影響を及ぼすおそれのある状態です。睡眠不足が積み重なり「債務超過」の状態に陥ると、生活や仕事の質が低下するだけでなく、うつ病、がん、認知症などの疾病に繋がるおそれがあります。
子どもも大人も睡眠不足の現状を理解して意識を変えることを考えましょう。
 2025年5月26日 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進
2025年5月26日 たちばな台クリニック小児科 秋谷 進
*この記事は朝日新聞の学校の先生向けに連載している朝日新聞 先生コネクト【子どもを診まもる】を改変したものです。
【子どもを診まもる】睡眠不足 なぜ教室のあの子は授業中にいつも眠そうなのか? | 朝日新聞社 先生コネクト