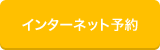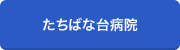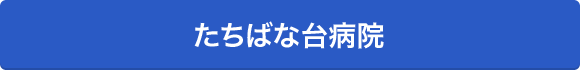健康教室
30回記念! たちばな台健康教室 パート1
2016年7月21日に第1回たちばな台健康教室を開催し、
なんと今回の2019年5月30日で・・・
第30回を迎えることが出来ました!
ありがとうございます!!
毎月1回の健康教室は準備に心が折れそうになる事も多々ありましたが、
聴講にお越し下さる皆さんの温かい笑顔に毎回励まされ、これまで「息切れ」することなく
続けてくることが出来ました。
という事で、第29回、30回のテーマは
「あなたに潜む! 息切れの4つの原因」
です。
まず呼吸とは
「生物が生命維持に必要なエネルギーを得るために、酸素を取り入れて養分を分解し、その際に生じた二酸化炭素を排出する現象」
と定義することが出来ます。
ここで呼吸に関連する3つの器官を考えてみましょう。
❶ 気道~肺:空気を吸い酸素を取り込む。空気を吐くことで二酸化炭素を排出する。
❷ 血液:肺から酸素を取り込み各臓器に供給。また各臓器から二酸化炭素を取り込み肺に運ぶ。
❸ 心臓:血液を各臓器に送りだすポンプ機能を有する。
これらの器官に障害が存在すれば、正常な呼吸を維持することが出来なくなり息切れが起こります。
息切れを生じる呼吸器疾患の代表として
「COPD」があります。
COPDとは
「タバコを主とする有害物質を長期に吸入暴露することで生じた肺の炎症性疾患」と定義される通り、
そのほとんどがタバコの煙によって生じます。
タバコの煙に含まれる有害物質が肺の構造を破壊したり、気管支に慢性的な炎症を起こすことにより換気障害を引き起こすのです。
COPDは簡単な検査で診断することが出来ます。
それが呼吸機能検査です。
「吸って吸って吸ってー、ぷーっと吐いて―ーー」の肺活量の検査を思い出してください。

喫煙をしていて最近息苦しいという方、簡単な検査ですので一度測定をしてみましょう。
COPDは早期発見・早期治療が大切です。
さて、治療の最優先はもちろん「禁煙」です。
禁煙しなければいけないことはわかっていてもなかなか踏み切れない方も多いのではないでしょうか?
自力での禁煙成功率は非常に低いことがわかっています。
もし禁煙を少しでも考えていらっしゃる方はお気軽に当院の「禁煙外来」へご相談ください。
皆さんの禁煙の力に少しでもなれればと思います。
https://map.sugu-kinen.jp/p/kinenmap/dtl/0000049388/?&his=al1,al2,al3,nm
第28回 たちばな台健康教室 ~知っておきたい便秘のすべて~
院長の山嵜です。
今日はたちばな台クリニック 月一回恒例の 健康教室を開催いたしました。
ようやく少し暖かくなり、桜も咲き始めた季節のせいか、それとも「便秘」というタイトルが皆さまのご要望にお応えできたのか、なんと82名の皆様にお集まりいただきました!
これまでに開催致しました健康教室来訪者数最高記録です。本当にありがとうございました。
今回のテーマである「便秘」は大きく2つに分類されます。
1.器質性便秘
: 腫瘍や炎症など大腸に形態的な病的変化を認めるもの
2.機能性便秘
: 大腸の排便機能に何らかの障害が起こり便秘となった状態
まずは器質性便秘でないかどうかの検査が重要です。
検査には大腸がん検診で用いる「便潜血検査」を第一に行います。
便潜血が陽性であれば大腸内視鏡による精密検査を受けて器質的異常がないかどうかを評価して下さい。
さて、器質的な異常が見られない場合には機能性便秘として診療を行っていきます。
この機能性便秘もさらに2つに分類することが出来ます。
❶ 排便回数減少型
: 排便回数や排便量が減少し、糞便が大腸に貯留することで腹部膨満感や腹痛をもたらします。
❷ 排便困難型
: 直腸や肛門の排便機能が低下し、直腸内の糞便を十分に排出できないため残便感を自覚する。
排便困難型の方の中には骨盤底筋群の筋力低下による便秘の方もいらっしゃいます。
そんな方には、椅子に座った姿勢で肛門を閉めるように力を入れる「骨盤底筋トレーニング」が非常に手軽でお勧めです。
聴講にお越し下さった皆さんは、一緒にやって頂きましてありがとうございました。
ぜひご自宅でも続けて頂けたらと思います。
そんな便秘の治療法ですが、まずは生活習慣による改善が第一となります。

食事ではやはり食物繊維が重要になります。
便秘に対しては食物繊維は必要最低限の摂取が望ましいとされています。
男性では20g/日、女性では18g/日が目標と定められておりますが、実際には男女それぞれ14.0g、13.6gと摂取不足であるのが現状です。
この食物繊維には3つの効果があると言われています。
1.食物繊維が便の核となり量を維持することが出来る
2.大腸の蠕動運動を促進し、大腸内に水分を分泌させる胆汁酸を吸着し大腸へ運搬する
3.腸内細菌の栄養となり、大腸粘膜のエネルギー源となる有機酸を産生する
今回食物繊維をたっぷり含むメニューとして当院栄養士の南先生がご紹介したのが・・・

こちら「ごぼうハンバーグ」です。
一食で約6gの食物繊維を摂取することがあります。
レシピをご希望の方はぜひスタッフまでお声かけ下さい。
さて、慢性便秘に対する薬物治療ですが、近年使用できる薬剤の種類が増え、患者様一人一人の症状に適した下剤を選択することが出来るようになりました。
薬物治療
ここでは慢性便秘の薬物治療の基本的スタンスとして
「非刺激性下剤」の定期服用 + 「刺激性下剤」のレスキュー使用
という考え方があることを念頭に置いて頂ければと思います。
「非刺激性下剤」
刺激が少なく、腹痛や耐性を生じにくい下剤
※酸化マグネシウム、ポリエチレングリコール、ルビプロストン、リナクロチド、エロビキシバットなど
「刺激性下剤」
腸管の収縮を誘発し、便秘を改善させる下剤
※センノシド、ビサコジル、ピコスルファートナトリウムなど
日本では刺激性下剤が多用されていますが、長期連用により耐性が出現し、難治性便秘になる事がありますので注意が必要です。
薬物治療の詳細に関しましてはまた別の機会にブログで紹介させて頂こうと思います。
もし便秘や現在の薬物治療にお悩みの方がいらっしゃいましたらぜひお気軽にご相談を頂けましたら幸いです。
これからも皆様に役に立つ情報をお届けし続けたいと思いますので、たちばな台健康教室を今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
第27回たちばな台健康教室 ~糖尿病は完治できる?~
院長の山嵜です。
少し暖かくなるとともに花粉症の方にはつらい季節になって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
2月の健康教室は糖尿病についてお話をさせて頂きました。
冷たい小雨の降る中70名弱の皆様に参加して頂きました。
本当に有難うございました。

糖尿病の原因には大きく2つあります。
❶ インスリン抵抗性の増大
❷ インスリン分泌低下
過食などにより脂肪細胞が肥大するとアディポネクチンの分泌が低下し、TNF-αなどの炎症を惹起するアディポサイトカインが増加することでインスリンの作用が低下してしまいます。
また日本人は欧米人に比べ人種的にインスリン分泌能が低下していることが知られています。
そのため日本人では欧米人に比べ、軽度のインスリン抵抗性増大により糖尿病を発症してしまう事になります。
今回の講演では、運動療法によるインスリン抵抗性の改善とアディポネクチン分泌の増大効果についてお話させて頂きました。
また管理栄養士の南先生からは地球会食とDASH食をみっくすさせたMind食、そして食物繊維についてお話をして頂きました。

昨年Cell Metabolismに掲載された「DIRECT」試験では肥満を伴う2型糖尿病患者に厳格な食事・運動療法を施行し減量を行ったところ、64例中 29例 (46%) で糖尿病が改善・緩解したことが示されました。
減量により肝臓に含まれる脂肪は16.0%から3.1%に減少。膵臓に含まれる脂肪も減少していました。
糖尿病が緩解した群としなかった群では、食事10分後のインスリン分泌能に有意差があり、緩解群ではインスリン分泌能が改善。
この結果は低下した膵β細胞の機能がリセットされ改善したことを示唆しています。
糖尿病は「一度かかれば、生涯完治することはない」とされていましたが、発症早期より生活習慣を改善することで完治できる可能性があるのだという事を示唆する非常に印象的な報告だと思います。
今回の講演では新しい糖尿病薬についてもお話しする予定でしたが、生活習慣の改善が予想以上に密度の濃い内容になってしまったため薬の話まですることが出来ませんでした。
そちらにつきましてはまたぜひ次の機会に。
それではまた皆様のご参加を心よりお待ちしております。
1月の健康教室を開催いたしました!
管理栄養士の南です。
本日は2019年最初の「コレステロール」をテーマに健康教室を行いました。
小雨の降る中とても寒い日ではありましたが過去最大74名の方にご参加いただき
ありがとうございました。
予想を超える方にお越しいただき、受付の混雑や配布資料の急きょ追加など嬉しい
悲鳴でしたがご不便をおかけしてしまった方には申し訳なく思います。
今月から講師の山嵜院長を含めスタッフ3名での運営になっておりますが
スムーズに運営できるよう検討してまいります。
本日の内容につきましては、追ってご報告させていただきます。
今日の写真を少々ご紹介!
取り急ぎ開催のご報告をさせていただきました。
次回は、2月28日(木)午前10:00~ たちばな台クリニック4階にて
糖尿病は完治できる? ~食事/運動の可能性と最新の薬物治療~
お誘いあわせの上、お気軽にお越し下さい。
健康教室レポート「ロコモを予防しよう ロコモティブシンドロームとは?」
平成30年10月の健康教室のテーマは、
「ロコも予防をはじめましょう ロコモティブシンドロームとは?」
です。
運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態を
「ロコモティブシンドローム(略称:ロコモ、和名:運動器症候群)」といいます。
進行すると介護が必要になるリスクが高くなりますので、日常生活に密着した病気と言えるでしょう。
ロコモは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態をいいます。進行すると日常生活にも支障が生じてきます。
人は骨や関節、脊髄、筋肉、神経などによって身体を支えたり、動いたりしています。
こうした器官を総称して運動器といいます。誰しも高齢になれば運動器の機能が低下していくものですが、現代のような高齢社会では、それが要介護などのリスクにつながる大きな要因となってしまいます。そこで、一人ひとりが日頃から自身の運動器の状態を認識し、チェックや早めの対策を行うことで長く健康な身体を維持できるよう発信されたキーワードがロコモなのです。
内臓面から健康を考えるメタボ(メタボリックシンドローム)という言葉はみなさんご存知ですね。ロコモはその運動器バージョン、そう考えればわかりやすいかも知れません。
こんな状態は要注意!チェックしよう 7つのロコモチェック
① □ 片脚立ちで靴下がはけない
② □ 家の中でつまずいたり、すべったりする
③ □ 階段を上がるのに手すりが必要である
④ □ 家のやや重い仕事が困難である
⑤ □ 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である
⑥ □ 15分くらい続けて歩くことができない
⑦ □ 横断歩道を青信号で渡りきれない
ロコモは、既に国民病とも言える疾患です。ロコモを引き起こす運動器障害には、2つに分類されます。
1つ目は運動器自体の疾患です。
高齢化の進展と共に運動器の障害も増加しています。運動器障害は痛みを引き起こす要因にもなり、関節痛を主訴とする症例では、主に変形性膝関節症があり、これは関節と関節の間の軟骨がすり減り痛みを伴う疾患です。また、骨が弱くなり骨折しやすくなる骨粗しょう症も代表的な疾患です。最近の調査によれば、変形性膝関節症の患者数は2400万人。骨粗しょう症を含めると4700万人とも言われ、運動器疾患の予防は今後ますます重要になってきます。
2つ目は、加齢による機能不全です。筋力低下などが上げられますが、ロコモ中でもすごく筋力低下している状態をサルコペニア(サルコ=筋力、ペニア=低下)と言います。これは、加齢により筋肉量が低下し、筋力低下や身体機能の低下が起こる事です。
サルコペニアを予防するポイントは、「栄養」と「運動」です。
まず、「栄養」では、低栄養に気を付けなければなりません。低栄養とは、体を維持する栄養が足りない状態です。
元気がない・著しくやせている(るい痩)・意図しない体重減少がある場合は、要注意です。低栄養にならないようにするためには、やはりしっかり食べることです。足りない栄養を補うために栄養補助食品を取り入れる事もあります。ご要望があれば、当院の管理栄養士がご相談をお受けしますのでお気軽にお声かけ下さい。
2つ目の「運動」ですが、ロコモサポートドクターの山嵜先生からは、生活のちょっとした合間に出来るスクワットと片脚立ちをご提案させて頂きました。
そして今回は、スペシャルゲストとして鴨志田地域ケアプラザと青葉区役所より3名お招きして、『ハマトレ』をご指導い頂きました。
『ハマトレ』とはロコモを予防するため、横浜市が高齢者の「歩き」に着目して開発したトレーニングです。 高齢者の姿勢や歩き方の特徴から、猫背・姿勢改善、傾きの改善、股関節の伸展、足関節の動き、バランス力の向上の「歩く」に関わる5つの要素を取り入れた20種類の運動からできています。 ストレッチやウォーキングなどとあわせて行うと効果的です。ハマトレの動画をご覧になりたい方は、横浜市のホームページを検索して下さい。また、お住まいの区役所、地域包括支援センターでDVDの貸し出しもしているようです。
いつまでも元気で笑顔でいられるように「ロコモチェック」と「ロコモ予防」をぜひ続けましょう。
健康教室レポート『災害時、いざという時どうしますか?』~知って欲しい日常の備えと災害時の行動~
講師の山嵜院長は、災害時地域医療対策委員会の理事として青葉区で災害が起きた際にどのように対応したよいか毎月対策をたてています。
今年は、平成30年7月豪雨、大阪府北部地震、北海道胆振東部地震など、いつ身の回りに災害が起こるか、起きたらどうするか改めて考えさせられます。
平成30年7月豪雨で被害のあった岡山県倉敷市真備町では防災のためのインフラ整備が今まさに行われる矢先の災害でした。防災整備にはお金や時間がかかるため、まず自分自身で出来ること考える必要があります。青葉区では、災害の被害予測を地図にしたハザードマップが作成されています。これを用いて自分の住居や勤務先の被害予測を事前に知っておく事が重要です。
私たちの暮らしている横浜市は今後、南海トラフ地震や首都直下型地震に備える必要があります。青葉区の被害想定は死者や負傷者の数は少ないと予測されていますが、停電、断水、インフラが機能しなくなるなど、家で生活する事が困難になり相当の数の被災者が発生し避難を余儀なくされる可能性が高くなると予測されます。
それでは大地震が発生したらどうするか?
在宅中に緊急地震速報が鳴ったら・・・
- 揺れに備えて頭を守り、大きな家具から離れる。丈夫なテーブルの下などに隠れる。慌てて外に出ると危険です。
- 火を消して、戸を開ける。停電が復旧した時に暖房器具などの家電の電源が入り火災を起こしやすくなるのでブレーカーを落とすと良いでしょう。
どんなときに避難が必要か?
生活が不便に感じたら避難所に向かうと良いでしょう。しかし、自分の避難所を知らないと困るので事前にハザードマップ等で調べましょう。
避難所にはいろいろな備蓄品が備えてあり、その他に地域定点診療拠点が設置され医療関係者が治療やトリアージを行います。
トリアージとは?
大事故や災害などで多数の患者発生したときに緊急度に従って治療の優先順位を付けることです。限られた人的、物的医療資源を最大限有効に活用し、なるべく多くの患者の生命を助けます。
地域定点診療拠点で行われる事
- 医師等が負傷者のトリアージを行う。
- 医師等が軽症者の診療を行う。
- 重症者・中等症者を拠点の運営委員等(各自治体の皆さんの力が必要)が病院へ搬送する。
- 医療チームが他の防災拠点に巡回診療を行う。
避難所に何を持って行きますか? 最低限の持ち物
- 現金:1,000円札、100円、10円(お釣りが不足するため小銭が便利)
- 水:500mlペットボトル数本
- 非常食:缶詰、ビスケット、飴など
- ティッシュ、ウエットティッシュ、タオル
- 懐中電灯、ラジオ
- カイロ、防寒具
- 携帯電話の充電器、予備バッテリー
- 身分証(運転免許証・保険証・パスポート等)
- 眼鏡
- 薬(1週間ぐらい予備があると良い)
薬がなくなったら…
従来薬局では、処方箋無しでは医薬品の販売は禁止されています。しかし、災害時に限り医師の診療や処方箋の交付が困難な場合には、後日医師から処方箋を書いてもらうことを条件に慢性疾患治療薬に限り処方箋無しで調剤することができます。
しかし、かかりつけ医が停電など被災している場合や別の診療所に受診した場合、薬の内容がわかりません。薬を証明するにはお薬手帳を携帯することが大事です。
災害は突然おそってきます。今から十分な準備を行ってください。